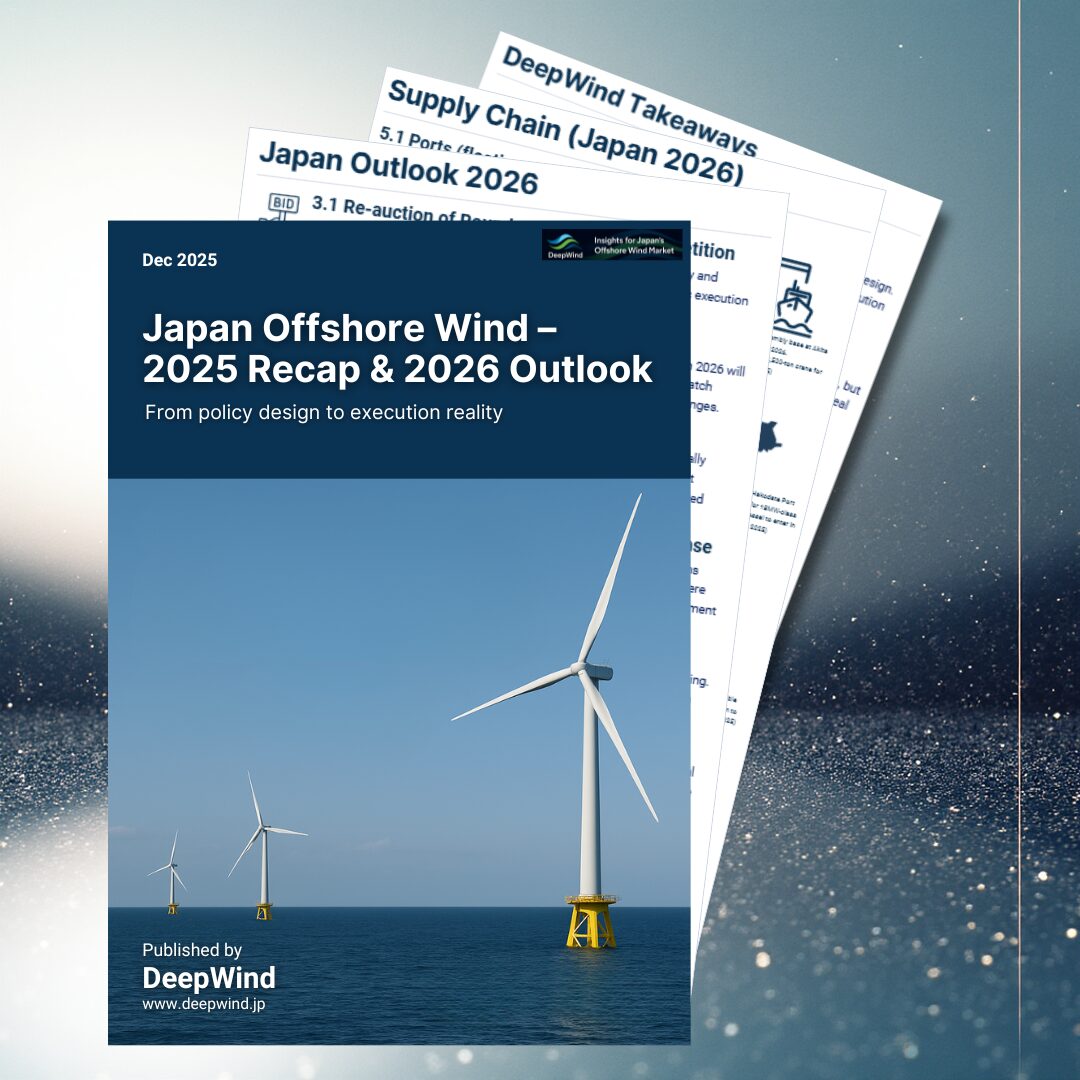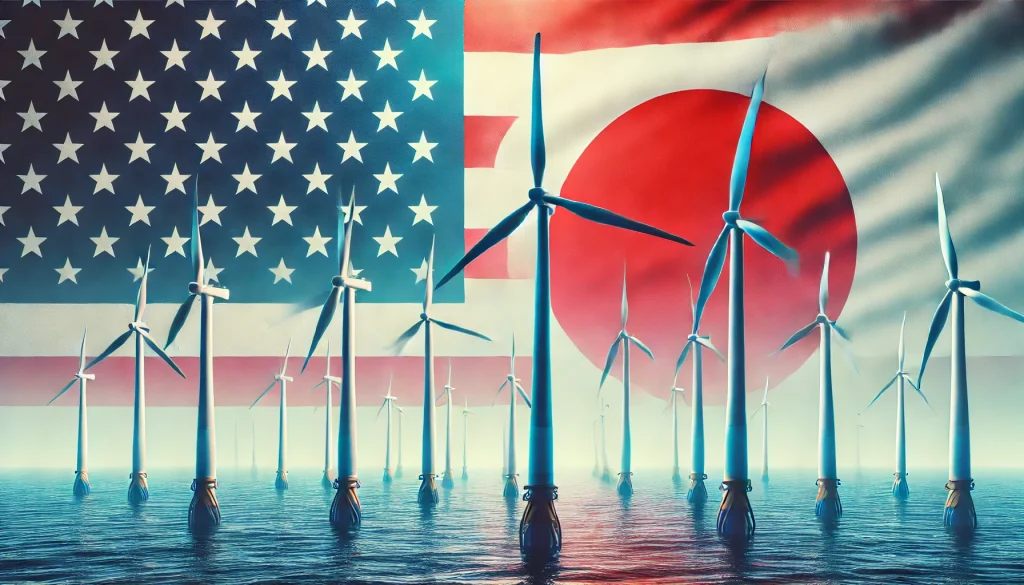日本の洋上風力市場をどう見るべきか
日本の洋上風力市場は、ここ数年で急速に注目を集めてきました。政府目標の設定、入札制度の整備、国内外プレイヤーの参入など、表面的には「市場が立ち上がりつつある」ように見えます。しかし一方で、案件の停滞や撤退、投資判断の慎重化といった動きも同時に進行しており、市場の実態は決して単純ではありません。
この違和感の正体は、日本の洋上風力市場が単一の要因で動いているわけではない点にあります。技術、政策、投資環境、コスト構造、サプライチェーン、そして需要側の要請が相互に絡み合い、全体として市場の進展速度と方向性を規定しています。どれか一つだけを切り取っても、市場全体を正しく理解することはできません。
本Pillar記事では、日本の洋上風力市場を「成長しているか/していないか」という二元論ではなく、どの条件が市場を前進させ、どの条件がブレーキになっているのかという構造面から整理していきます。
なお、日本市場における洋上風力の立ち位置や、他電源との比較を含めた俯瞰的な視点については、以下の記事で詳しく整理しています。
👉 日本の洋上風力はなぜ「簡単ではない」のか|構造的な制約整理
日本の洋上風力市場の現在地(2024–2025)
2024年から2025年にかけての日本の洋上風力市場は、「拡大フェーズに入った」と表現されることが少なくありません。しかし、実態を見ると市場はむしろ踊り場に近い状態にあります。案件数は増えているものの、すべてが順調に前進しているわけではなく、計画の見直しや延期、事業性再評価が相次いでいます。
政府は中長期的な導入目標を掲げ、制度的な枠組みも一定程度整備してきました。一方で、事業者側の投資判断は以前よりも明らかに慎重になっています。これは「市場が失敗した」ことを意味するものではなく、初期の期待と現実の条件がすり合わされる段階に入ったと捉える方が適切です。
このギャップを生んでいる要因の一つが、政策目標と実装条件の時間軸の違いです。政策は10年、20年単位での導入量を描きますが、個別プロジェクトは数年以内に投資回収の見通しを立てなければなりません。このズレが、市場全体としてのスピード感に影響を与えています。
また、洋上風力は「一度走り出せば量産効果で加速する」という前提で語られがちですが、日本市場では港湾、施工、サプライチェーンといった物理的制約が強く、必ずしも直線的な拡大が可能な構造にはなっていません。その結果、案件ごとの差が大きくなり、「進む案件」と「止まる案件」が同時に存在する状況が生まれています。
こうした「踊り場」とも言える状況は、単一案件の問題というより、市場全体の成熟プロセスとして捉える必要があります。実際には、分野ごとに進捗の濃淡が生じており、サプライチェーン、政策、需要側でそれぞれ異なる動きが見られます。
日本市場の足元の動きを、政策・産業・投資の観点から整理した分析は、以下の記事で個別に扱っています。
投資マネーはなぜ慎重になっているのか
日本の洋上風力市場を語る上で欠かせないのが、投資マネーの動きです。表面的にはESG投資やエネルギートランジションへの関心は依然として高く、洋上風力は「投資テーマ」として注目されています。しかし、実際の投資判断を見ると、以前よりも慎重な姿勢が目立ちます。
この背景には、単なる金利上昇やマクロ経済環境の変化だけでなく、洋上風力特有のリスク構造に対する再評価があります。特に日本市場では、制度変更リスク、政治的発言リスク、自然条件リスクが重なり、将来キャッシュフローの不確実性が高く評価されがちです。
海外投資家の視点から見ると、日本市場は「成長余地が大きい一方で、ルールの再設計が続いている市場」と映ります。これは機会であると同時に、参入タイミングを慎重に見極める理由にもなります。短期的なリターンを重視する資金ほど、様子見姿勢を強める傾向があります。
さらに、政治的な発言や国際情勢も無視できません。特定の国・地域における再エネ政策への否定的な発言は、直接的な制度変更がなくとも、投資家心理に影響を与えます。日本市場自体の制度とは別次元で、グローバルな投資環境が評価軸に影響する点は、これまで以上に重要になっています。
結果として、日本の洋上風力市場では「資金はあるが、無条件には入ってこない」状態が生まれています。これは市場が成熟に向かう過程で避けられない現象でもあり、今後はどのリスクが管理可能で、どのリスクが構造的に残るのかを明確に示せる案件だけが選別されていくと考えられます。
投資家が見ているのは「市場規模」そのものではなく、リスクがどの程度コントロール可能かという点です。この評価軸は、個別プロジェクトだけでなく、国全体の制度設計や政治的メッセージにも影響を受けます。
実際、日本市場に対する投資スタンスの変化は、具体的なニュースや発言を通じて顕在化してきました。以下の記事では、その象徴的な事例を整理しています。
また、投資家・事業者が日本市場にどう向き合うべきかという観点は、以下の記事で戦略的に整理しています。
コスト・収益性が市場をどう制約しているか
日本の洋上風力市場が「制度上は前進しているように見える一方で、投資と開発が慎重化している」最大の理由は、コストと収益性のバランスが依然として成立しにくい点にあります。これは単なる一時的なコスト高ではなく、市場構造そのものに起因する制約です。
洋上風力は一般に「規模が大きくなれば安くなる」と理解されがちですが、日本市場ではその前提が完全には成立していません。理由は、CAPEX・OPEX・金融コストのそれぞれが、同時に下がりにくい構造を持っているためです。
CAPEX:設備規模は大きいが、固定費が重い
日本の洋上風力プロジェクトでは、風車大型化や案件規模の拡大が進んでいるにもかかわらず、CAPEXは想定ほど低下していません。主な要因は、基礎・施工・港湾・送電といったローカル条件依存のコスト比率が高いことにあります。
特に、港湾機能の制約や施工ウィンドウの狭さは、直接費だけでなく、工期遅延リスクを織り込んだコンティンジェンシーとしてCAPEXを押し上げます。これは設計や調達の工夫だけでは吸収しきれない要素であり、日本市場固有の「構造コスト」として残りやすい領域です。
OPEX:下げ余地はあるが、劇的改善は期待しにくい
OPEXについては、遠隔監視、ドローン点検、O&M体制の高度化などにより一定の改善余地はあります。しかし、日本近海の気象・海象条件を考慮すると、安全マージンを削ってまでコストを下げることは現実的ではありません。
結果として、OPEXは「少しずつは改善するが、LCOEを決定的に押し下げるほどには下がらない」という性格を持ちます。このため、CAPEXが高止まりしている状況では、OPEX改善だけで事業性を回復させるのは困難です。
金融条件とIRR:最大のボトルネック
日本の洋上風力市場で最も厳しい制約となっているのが、金融条件を含めたIRRの成立性です。CAPEX・OPEXが一定水準以上で推移する中、電力価格や制度収入が固定的である場合、IRRは構造的に圧迫されます。
さらに、台風・地震・施工遅延といった不確実性は、WACCの上昇や保険料増加として反映されます。これは個別事業者の努力では解消できず、市場全体として「リスクプレミアムが高止まりしやすい」状態を生み出します。
この結果、表面上は「発電コストが下がっているように見えても」、投資判断の前提となるIRRが成立せず、案件が進まないという現象が生じます。
撤退事例が示した現実
こうした構造は、個別企業の判断にも明確に表れています。象徴的なのが、洋上風力事業からの撤退や方針転換を余儀なくされた事例です。これらは単なる経営判断ではなく、市場構造が事業成立を許容しなかった結果と見る方が適切です。
また、Round1案件の撤退分析からも分かる通り、入札制度そのものよりも、落札後に顕在化するコストとリスクが事業継続を難しくしています。
これらの事例は、「今後コストが下がるはず」という期待だけで市場を評価することの危うさを示しています。
より具体的な数値分析や撤退要因の分解については、以下の記事で詳細に整理しています。
コストと収益性の問題は、単独では解決しません。制度、技術、サプライチェーン、金融が同時に改善されない限り、市場は部分的な前進にとどまります。次章では、こうした制約の中でなぜ浮体式洋上風力が再び議論の俎上に上がっているのかを、市場文脈から整理します。
なぜ今、浮体式洋上風力が市場テーマとして浮上しているのか
着床式洋上風力が直面しているコスト・施工・制度上の制約を背景に、日本市場では再び浮体式洋上風力が重要な市場テーマとして浮上しています。これは「技術が成熟したから」という単純な理由ではなく、着床式だけでは市場拡大が頭打ちになる構造が明確になってきたことによるものです。
言い換えれば、浮体式洋上風力は「次世代技術だから注目されている」のではなく、既存の延長線では解決できない制約への“現実的な代替案”として再評価されていると捉える方が、市場の実態に近いと言えます。
着床式市場の物理的・構造的な限界
日本周辺海域において、着床式洋上風力が適用可能な水深帯は限定的です。さらに、その多くは漁業利用、港湾利用、景観配慮などの制約を同時に抱えており、「理論ポテンシャル」と「実装可能ポテンシャル」の乖離が顕在化しています。
加えて、施工船・港湾・送電インフラといった要素は、案件ごとに競合が生じやすく、規模拡大による単純な効率化が効きにくい状況にあります。これにより、着床式だけで日本市場を継続的に拡大していくシナリオは、現実的な制約に直面しています。
浮体式は「コスト削減策」ではなく「空間拡張策」
浮体式洋上風力は、しばしば「将来コストが下がれば有望」と語られますが、市場文脈ではそれ以上に重要な意味を持ちます。それは、利用可能な海域そのものを拡張できるという点です。
着床式ではアクセスできない深海域や、沿岸から距離を取った海域を活用できることは、単に設備を増やせるという話ではありません。社会受容性、空間制約、送電計画といった複数のボトルネックを同時に緩和し得る選択肢として、浮体式が位置付けられています。
市場停滞局面で浮上する「第二の選択肢」
市場が順調に拡大している局面では、事業者も投資家も、リスクの低い既存技術を優先します。しかし、市場が停滞し、従来の延長線での成長が見えなくなったとき、初めて代替オプションが現実的な検討対象となります。
現在の日本市場は、まさにこの局面に差し掛かっています。着床式の案件形成が慎重化する中で、浮体式は「次のフェーズをつなぐための選択肢」として、政策側・事業者側の双方から再評価され始めています。
ただし、浮体式は“万能解”ではない
重要なのは、浮体式洋上風力が着床式の課題を自動的に解決する万能解ではないという点です。浮体式は、別のコスト構造、別の施工制約、別の金融リスクを伴います。
そのため、浮体式が市場テーマとして浮上している背景には、期待と同時に慎重な現実認識が存在します。市場関係者の多くは、「浮体式ならすべて解決する」とは考えておらず、「着床式の限界を補完する条件付きオプション」として捉えています。
浮体式への期待は高まっていますが、実装には着床式以上にシビアな条件が伴います。 最新の調査によれば、15MW級風車を搭載する場合、浮体重量は2万トンに達し、港湾には極めて高い地耐力と広大な作業ヤードが求められます。
浮体式特有の「重厚長大」な制約と、それに対応するためのインフラ戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。
👉 浮体式洋上風力「15MW時代」の港湾戦略とは?FLOWRA欧州調査を完全解読
この点を正しく理解しないまま浮体式を評価すると、過度な期待や誤った投資判断につながる可能性があります。
浮体式洋上風力がなぜ今、市場文脈で再浮上しているのかについては、以下の記事で背景を整理しています。
また、日本市場だけでなく、世界全体での浮体式導入フェーズを把握することは、過度な期待を避ける上で有効です。
次章では、こうした浮体式再評価の流れを踏まえつつ、サプライチェーンと実装能力が市場拡大をどこまで支えられるのかを整理します。
サプライチェーンと実装能力が市場を左右する
日本の洋上風力市場、とりわけ今後の成長余地を左右する最大の要因は、需要や政策目標ではなく、サプライチェーンと実装能力がどこまで現実に対応できるかという点にあります。市場拡大が進まない背景には、「計画はあるが、実行できない」という構造的なギャップが存在しています。
この問題は、浮体式・着床式を問わず共通していますが、特に案件規模が大きく、工程が複雑な洋上風力では、サプライチェーンの脆弱性が市場全体のボトルネックとして顕在化しやすくなります。
国内サプライチェーンは「量」ではなく「実行力」が課題
日本には、造船、鉄鋼、重工、建設といった基盤産業が存在しており、表面的には「洋上風力向けサプライチェーンの潜在力は高い」と評価されがちです。しかし実際には、洋上風力に特化した量産体制や実績の蓄積が不足しているという問題があります。
単発の受注や試作レベルでは対応できても、GW級案件を前提とした連続生産・工程管理・品質保証となると、対応可能な事業者は限定されます。このギャップは、計画段階では見えにくいものの、実行段階で顕在化し、市場の進行速度を大きく左右します。
象徴的事例としてのブレード事故(陸上風力)
サプライチェーンの脆弱性を象徴的に示した事例として挙げられるのが、秋田県で発生した陸上風力発電設備におけるブレード落下事故です。本事故は洋上風力ではなく陸上風力で発生したものですが、大型風車に共通するサプライチェーン上の構造的リスクを理解するうえで、示唆に富むケースと言えます。
この事例が示しているのは、単なる品質不良や個別トラブルではありません。ブレードの製造、長距離輸送、現地での据付、最終検査に至るまで、複数の工程が高度に連動する風力設備特有のリスク構造が、事故という形で顕在化した点に本質があります。
近年の風力発電ではブレードの大型化が急速に進んでおり、製造拠点、輸送経路、港湾・仮置き設備、施工精度のいずれか一つに問題が生じるだけで、プロジェクト全体が停止する可能性があります。これは特定の事業者や現場の問題というより、市場全体として大型設備を安定的に実装する経験が十分に蓄積されていないことに起因する構造課題と捉えるべきです。
👉 秋田・新屋沖ブレード事故が示したサプライチェーン上の課題
港湾・施工能力がスケールを制限する
洋上風力、とりわけ浮体式においては、港湾機能と施工能力が市場規模の上限を事実上決定します。大型部材の組立・保管・積出・曳航を前提とした港湾は限られており、既存港湾の転用にも時間と投資を要します。
施工面でも、作業船、係留・設置ノウハウ、気象ウィンドウの確保といった制約が重なり、「計画通りに作れる能力」そのものが希少資源となっています。このため、案件が増えれば増えるほど競合が発生し、結果として市場全体の進行が遅くなるという逆説的な状況が生まれます。
海外依存と内製化の現実的バランス
現時点では、日本の洋上風力サプライチェーンは、主要部材や施工ノウハウを海外に依存せざるを得ない状況にあります。これは短期的には合理的な選択ですが、同時に外部要因による不確実性を市場に持ち込みます。
一方で、すべてを国内で完結させる内製化を短期間で実現するのは現実的ではありません。実務的に重要なのは、どの工程を国内で担い、どこを外部に委ねるのかを戦略的に切り分けることです。この判断を誤ると、コスト増と工程遅延の両方を招くリスクがあります。
サプライチェーン全体の進捗と課題については、以下の記事で整理しています。
サプライチェーンと実装能力は、政策目標や投資意欲とは独立して、市場の成長速度を規定します。次章では、こうした制約の中で、投資家・事業者がどのような戦略を取り得るのかを整理します。
投資家・事業者はどう動くべきか(市場戦略の分岐)
日本の洋上風力市場は現在、「成長市場への初期参入フェーズ」から「戦略を選別すべき分岐点」へと移行しつつあります。案件数や政策目標だけを見れば拡大余地は残っているように見えますが、実務レベルではすべてのプレイヤーが同じ戦略を取れる局面ではなくなっているのが実態です。
この段階で重要なのは、市場全体の楽観的な成長シナリオに合わせることではなく、自社の立ち位置とリスク許容度に応じた戦略を明確に分けることです。
戦略はすでに分岐している
現在の日本市場では、投資家・事業者の動きは大きく三つの方向に分かれ始めています。
- 案件形成を継続し、次の制度・市場環境を待つプレイヤー
- 案件規模や関与範囲を絞り、限定的な参入に切り替えるプレイヤー
- 採算性・リスクの観点から撤退または一時停止を選択するプレイヤー
いずれの戦略も「正解・不正解」で評価できるものではなく、市場環境の変化をどう評価するかによって合理性が変わります。重要なのは、どの戦略を選ぶかよりも、なぜその戦略を選ぶのかを明確に説明できるかです。
投資判断を分ける最大の要因は「収益の見通し」
投資家・事業者の判断を最も強く分けているのは、LCOEやIRRといった数値そのものよりも、それらがどの程度の確度で実現できるかという見通しです。
着床式・浮体式を問わず、日本の洋上風力案件では、建設費、O&M費、工期、系統接続、制度変更リスクといった要素のばらつきが大きく、初期想定と実績の乖離が起きやすい構造にあります。この不確実性が、資本コストや投資判断に直接影響しています。
実際に、採算性を理由とした撤退や戦略見直しの事例は、市場の成熟不足を示す象徴的な動きと言えます。
政策・制度は「後押し」にはなるが「保証」ではない
日本の洋上風力市場では、政策や制度の存在がしばしば投資判断の拠り所として語られます。しかし実務的には、政策は事業成立を保証するものではなく、条件を設定するものに過ぎません。
過去の公募や制度設計を振り返ると、制度変更や前提条件の見直しが、事業者側の想定に影響を与えてきたことが分かります。政策リスクはゼロにはならず、むしろ市場が成熟するまでの過程では継続的に存在します。
電力需要側との接続をどう設計するか
投資戦略を考えるうえで、近年重要性を増しているのが、RE100やScope2対応といった需要側の論理との接続です。従来のFIT/FIP前提の発電事業だけでなく、電力需要家との関係性をどう構築するかが、市場戦略の幅を広げています。
ただし、ここでも過度な期待は禁物です。需要家ニーズは存在するものの、価格・供給安定性・契約期間といった条件が厳しく、すべての洋上風力案件が直接的に結びつくわけではありません。
実務的に現実的な市場戦略
以上を踏まえると、日本の洋上風力市場において現実的な戦略は、以下のように整理できます。
- 初期フェーズでは案件数を追わず、条件の揃った案件に限定して関与する
- 技術リスク・施工リスク・制度リスクを同時に取らない
- 撤退・縮小も含めた選択肢を事前に織り込んだ戦略設計を行う
これは慎重すぎる戦略に見えるかもしれませんが、市場が成熟途上にある局面では、無理に先行することよりも、失敗しないことの価値が高い場合も多くあります。
投資家・事業者にとって重要なのは、「日本の洋上風力市場は必ず成長するか」ではなく、「どの条件が整ったときに、自分は動くのか」を明確にすることです。
次章では、これまで整理してきた市場・コスト・サプライチェーン・投資戦略を踏まえ、日本の洋上風力市場をどう位置付けるべきかを総括します。
まとめ|日本の洋上風力市場はどこへ向かうのか
本記事では、日本の洋上風力市場を「政策目標」や「導入量見通し」ではなく、市場構造・コスト・サプライチェーン・投資行動といった実装側の視点から整理してきました。その結果として浮かび上がるのは、日本の洋上風力市場が成長か停滞かという二項対立では語れない段階に入っているという現実です。
着床式洋上風力は、物理的制約、施工能力、採算性の観点から、これまで想定されていたほど単純には拡大しないことが明らかになりつつあります。一方で、浮体式洋上風力は、深海域という新たな空間を開く可能性を持つものの、別のコスト構造と実装制約を伴います。いずれも「容易な成長ルート」ではありません。
また、市場拡大を支える前提とされてきたサプライチェーンや港湾・施工能力についても、需要の増加に自動的に追随できる状況にはありません。むしろ、実装能力そのものが市場成長の上限を規定する局面に入っており、「計画があること」と「実行できること」の差が、これまで以上に重要になっています。
こうした環境下で、投資家や事業者の戦略はすでに分岐しています。全員が先行投資を続ける局面は終わり、条件が整うまで待つ、関与範囲を限定する、あるいは撤退するといった判断も、十分に合理的な選択肢として成立する段階に入っています。これは市場の失敗ではなく、成熟前段階に特有の調整プロセスと捉えるべきでしょう。
重要なのは、日本の洋上風力市場を「必ず成功する成長産業」として扱うことでも、「もう期待できない分野」と切り捨てることでもありません。必要なのは、どの条件がそろえば、どの範囲で成立するのかを冷静に見極める視点です。
今後の市場は、全国一律に拡大するというよりも、条件の整った海域・案件・事業者から段階的に形成されていく可能性が高いと考えられます。その過程では、案件数よりも再現性、スピードよりも確実性が重視される局面が続くでしょう。
DeepWindは今後も、日本の洋上風力市場を「期待」ではなく「構造」として捉え、表面的な進捗や数値だけでは見えない実装上の論点を継続的に整理していきます。本Pillar記事が、市場を評価する際の共通の思考フレームとして活用されることを意図しています。
「日本の洋上風力は目標ではなく成立条件で止まっている」——📘 DeepWind Premium Report
商業性・コスト・サプライチェーン・Round4/再入札の視点から構造整理した意思決定向けレポートです。
レポートを見る(Gumroad)
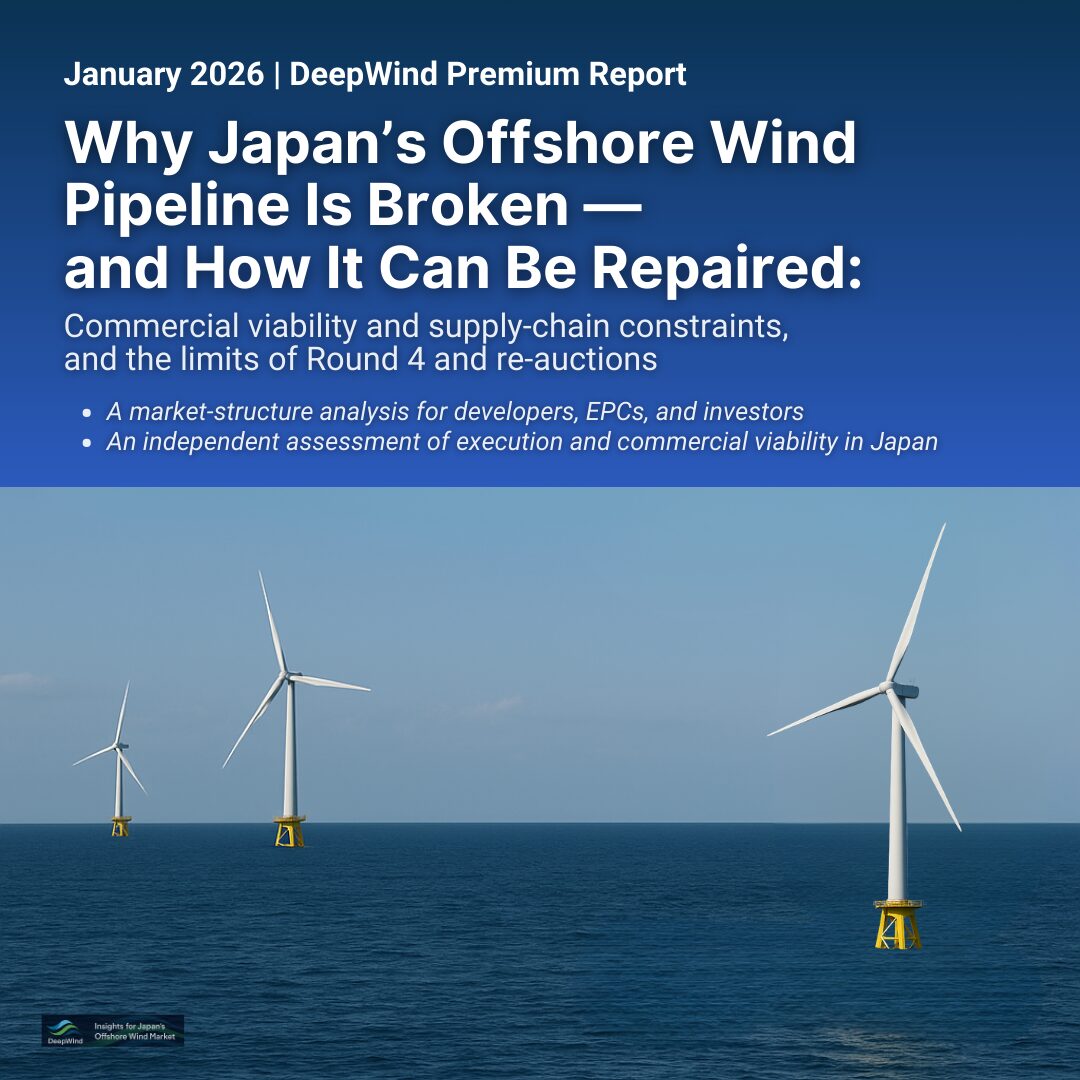
- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説
- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説
- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介
- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介
- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説