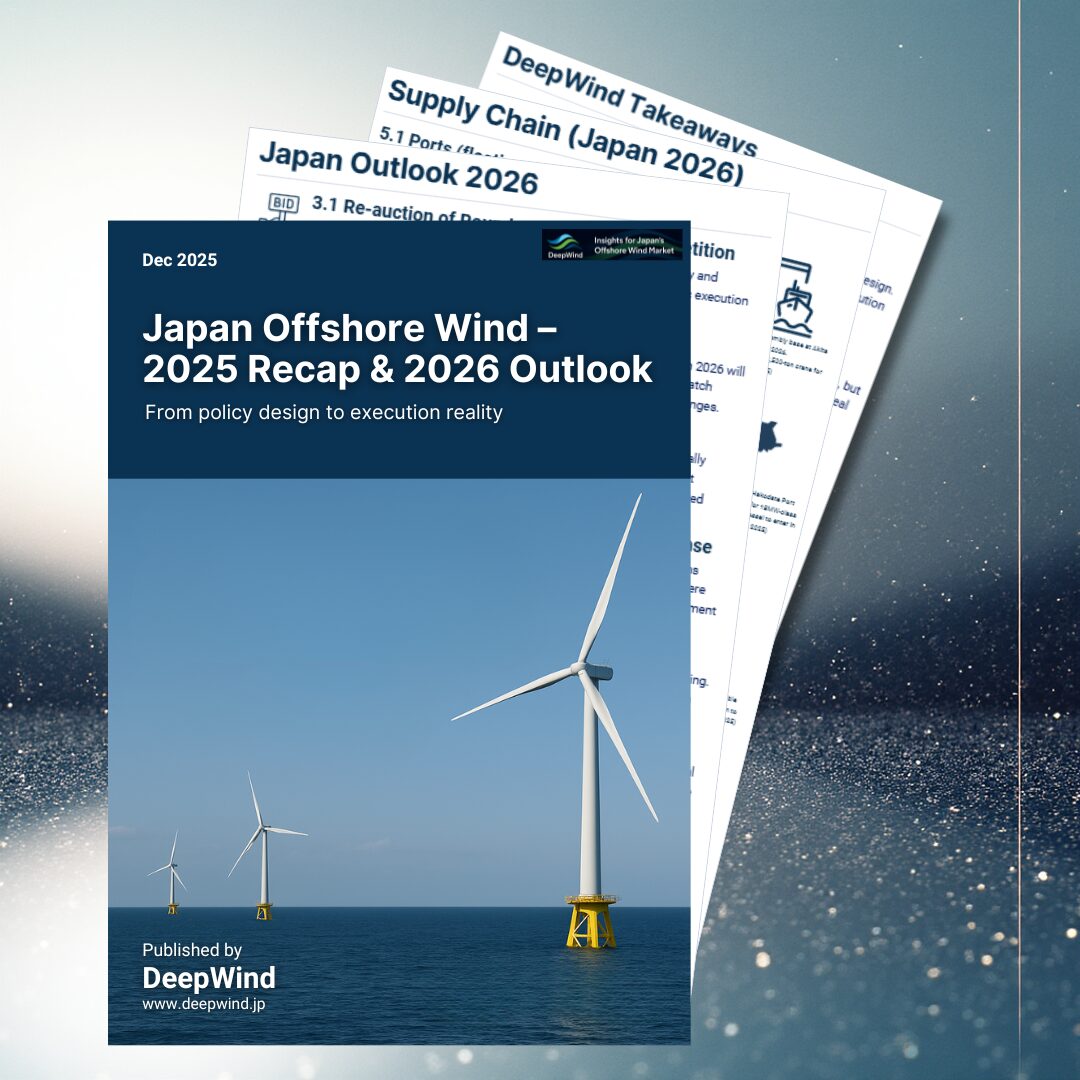DeepWind Weeklyは、日本の洋上風力発電に関する注目ニュースを毎週お届けするニュースダイジェストです。
本記事では、2025年9月に発表された主要トピックを週ごとに振り返ります。
2025年9月第1週
1. 秋田県沖洋上風力、再公募へ – 政府が要件見直しを表明
三菱商事の撤退を受け、秋田県由利本荘市沖および能代市・三種町・男鹿市沖の洋上風力プロジェクトについて、政府は公募要件を見直したうえで再公募に踏み切る方針を示しました。経産省は年内をめどに新要件を提示予定。地元自治体からは早期実施を求める声が相次いでいます。
2. 男鹿・潟上・秋田沖の洋上風力、企業連合が潟上市に本社設置 – 誘致企業に認定
JERAなどで構成される男鹿・潟上・秋田オフショアグリーンエナジー合同会社が潟上市に本社を設置。秋田県から「誘致企業」に認定されました。計画では着床式風車21基(約260m級)を建設し、30万世帯分の電力を供給。運転開始は2028年6月を予定しています。陸上送変電工事も開始され、O&M拠点は2027年3月に男鹿市船川港に設置される計画です。
3. 三井物産、村上・胎内沖洋上風力を「予定通り進行」 – 陸上工事を10月開始へ
三井物産が参画する「村上胎内洋上風力発電」事業は、当初4月開始予定だった陸上工事を10月から開始する方針を明らかにしました。元請け業者の選定も完了しており、2029年6月の運転開始を目指して準備を進めています。
同社は「資材高騰や為替の影響でコスト面の困難に直面している」としつつも、「全体工程に影響がないよう進めている」と説明。設置計画では38基の風車(総出力684MW)を建設し、約92平方kmの海域で開発が進行します。
4. 青森県沖洋上風力、厳しい環境も「計画通り進める」 – 東北電力
三菱商事連合の撤退発表を受けて注目が集まる青森県沖(つがる市・鰺ヶ沢町沖)の洋上風力事業。東北電力は「現時点では計画通り進める」と表明しました。最大出力61.5万kW、2030年6月運転開始を目指す案件で、JERAやグリーンパワーインベストメントと共同で開発を進めています。
東北電力は、円安や資材価格高騰の影響を認識しつつも「協業会社と連携し、適切に対応を検討中」と説明。さらに「国の制度整備に期待する」と述べました。
2025年9月第2週
1. 風力発電の廃棄費用を積立義務化へ
経済産業省は2027年度から、風力発電の廃棄費用積立を事業者に義務化する方針を示しました。設備廃棄時の不法投棄を防ぐ狙いです。
2. 東洋建設がケーブル敷設船を公開
東洋建設は関海事工業所と連携し、ケーブル敷設船と埋設機を公開しました。NEDO支援のもと、2026年度には自航式船を導入予定。施工の効率化とコスト削減を目指します。
3. 北九州市、響灘に浮体式拠点を整備へ
響灘では既に着床式25基と国内初の浮体式商業運転が稼働中。北九州市は国内外市場を視野に入れた「浮体式の産業拠点」整備を進める方針です。
2025年9月第3週
1. 政府、落札済み洋上風力事業への追加支援を容認
三菱商事の撤退を受け、政府は海域利用期間を30年超に延長可能とするなど、追加支援策を打ち出しました。公平性よりも再エネ普及の国策を優先する姿勢です。
2. 自治体、経産省に採算確保のための支援を要望
新潟、青森、山形、長崎の自治体代表が経産省を訪れ、物価高や為替影響に対応できる支援を求めました。事業継続のため安定した制度整備が必要と訴えました。
3. 関電・JERAなどの浮体式コンソーシアム、英EMECと連携
関西電力やJERAが参加する浮体式洋上風力技術研究組合(FLOWRA)は、英国スコットランドの欧州海洋エネルギーセンター(EMEC)と覚書を締結。実海域での浮体式技術検証を加速させ、日本の技術力強化を図ります。
2025年9月第4週
1. 三菱撤退で秋田県内72社に影響、知事が再公募を要望
秋田県が実施した調査によると、三菱商事が「能代・三種・男鹿沖」および「由利本荘沖」の洋上風力発電事業から撤退したことで、県内72社が影響を受けたことが明らかになりました。調査対象298社のうち24%に相当し、このうち12社はすでに数十億円規模の先行投資を実施していました。
影響は製造業、建設業、小売・卸売など多岐にわたり、60社は受注を見込んだ事業計画を立てていました。鈴木知事は9月19日、経産省を訪れ武藤経産相に速やかな再公募と柔軟な支援策を要請しました。
知事は「国家プロジェクトに地域を挙げて挑戦してきた。挑戦意欲を失わせない支援が必要」と強調。政府はすでに海域利用期間の延長など再公募に向けた制度改正を進めていますが、今回の事例は地域サプライチェーンの脆弱さを浮き彫りにしています。
2. 千葉・秋田の両知事、早期再公募を要望
三菱商事の撤退を受け、千葉県の熊谷俊人知事と秋田県の鈴木知事が武藤経産相と会談し、銚子市沖と秋田沖の洋上風力事業について速やかな再公募を求めました。熊谷知事は「二度と撤退が起きないよう、事業を完遂できる制度見直しを」と強調しました。
経産省は、年内に制度改正の方向性を示すとし、公平性を担保しながらも再公募を急ぐ考えを表明。また、銚子地域で設置された「未来創造会議」などの地域振興策を継続的に支援する意向も示しました。
今回の要請は、超低価格入札と建設コスト高騰が事業の持続可能性を揺るがす中で行われたもので、長期にわたる事業の安定性を担保する仕組み作りが求められています。
3. 福井・あわら市沖の洋上風力、経済効果1230億円を試算
「準備区域」に指定されているあわら市沖の洋上風力について、福井県は30年間で最大1230億円の経済波及効果と約6880人の雇用創出を試算しました。事業規模は35万kW、総事業費は約4836億円とされています。
秋田・千葉での撤退が全国に波及する懸念がある中、県は「現時点で撤退の意向を示す事業者はいない」として、誘致活動に影響はないと強調。建設から撤去までを含む30年間の経済効果を提示することで、地域振興の柱として期待を高めています。
全国的には採算性への懸念が強まっていますが、県は地元関与と政府支援を組み合わせて投資を確保する姿勢を示しています。
今月のまとめ
2025年9月は、日本の洋上風力市場において事業環境の厳しさと政府の追加支援策が大きな焦点となりました。三菱商事の撤退を契機に、秋田や千葉では再公募の動きが加速し、自治体や地元企業への影響が浮き彫りになりました。一方で、国は海域利用期間の延長や制度見直しを通じて、長期的な事業継続を支える姿勢を示しています。
また、北九州市の「浮体式」拠点整備や、福井県あわら市沖の経済効果試算など、地域発の取り組みも前進しました。洋上風力が単なる発電事業にとどまらず、雇用創出や産業振興の柱として位置づけられていることが明確になっています。
技術開発面では、ケーブル敷設船の公開や浮体式コンソーシアムの国際連携など、インフラ整備と技術基盤の強化が進展。市場の不確実性が高まる中でも、日本は着床式・浮体式双方で成長の可能性を模索し続けています。
総じて9月は、撤退のリスクと制度改革の動きが交錯する転換点となり、洋上風力の持続可能な成長に向けた課題と可能性が同時に浮き彫りになった1か月でした。
📘 2025年 洋上風力ニュース総まとめ
2025年を通じて起きた主要な洋上風力ニュースを一挙に振り返り。
プロジェクト進展、政策動向、浮体式技術のトピックを網羅しています。
👉 年間まとめ記事はこちら
➡ 2025年の洋上風力ニュースダイジェスト
もっと深く知りたい方へ:DeepWindの注目カテゴリーをチェック!
- 🔍市場動向・分析 – 日本の洋上風力市場の最新動向と注目トピックをわかりやすく解説
- 🏛️政策・規制 – 法制度、促進区域、入札制度など、日本の政策枠組みを詳しく解説
- 🌊プロジェクト – 日本国内の洋上風力プロジェクト事例をエリア別に紹介
- 🛠️テクノロジー&イノベーション – 日本で導入が進む最新の洋上風力技術とその開発動向を紹介
- 💡コスト分析 – 洋上風力のLCOEやコスト構造を日本の実情に基づいて詳しく解説